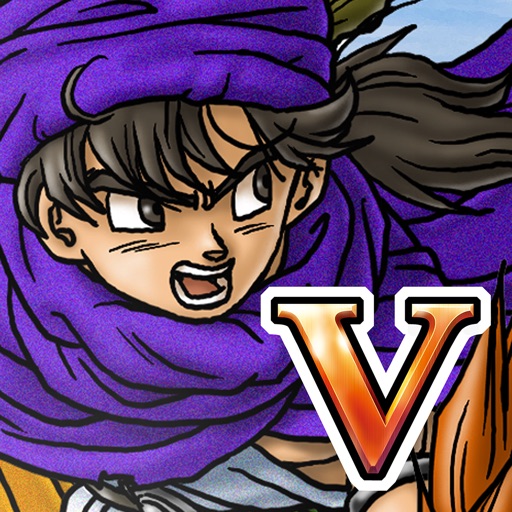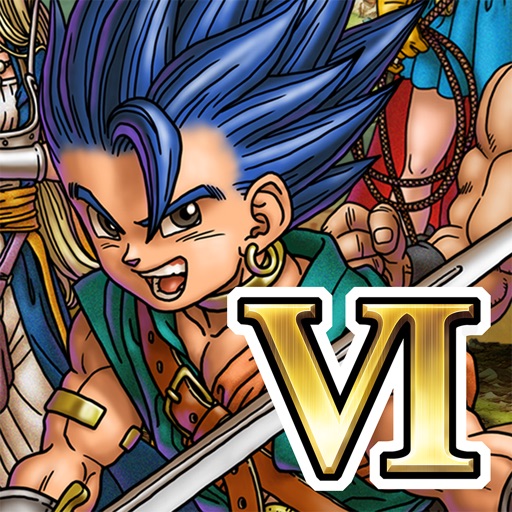「たったひとつの絆」までの
『セレドの町』の関連クエストです。
以降の世界の動きは参照せずに完結しているため、今後新要素や新情報が増えた場合も上記の時間軸の範囲を前提でご覧ください。重要なネタバレは上記のクエスト範囲に含まれていますが、細かい箇所のネタバレも完全に防ぐには「メガルーラストーンを手に入れられるあたりまで」と「魂がつまびく音色」(トゥーラのオルゴールをもらえるところ)を終えている必要があります。
原作に沿っていますが、ゲーム中では明示されていない言動や未来設定でところどころを補完しています。
ケータイでコツコツ書いたので一応は読み直しましたが誤字脱字が多いかもしれません。神経をとがらせて商用に執筆したものではなくダラダラ書いたものなので、重複描写や語尾が同じ文章だらけでも笑ってゆるしてください。
 わたし
わたし
セレドの子供たち…というかブラト町長のところの姉妹のことが気がかりでなりません…。将来的に(あるいはドラクエ10ほとんど進めてない私が知らないだけで既にもう何かあるのかもしれないけど…)なんかこう、また会えてくれ…。あの二人が一緒に時間を過ごす理由と結末を…。
 わたし
わたし
…と思っているけれど、ドラクエ10は終わらないドラクエだから展開可能要素をたくさん残したまま先へ先へ行くのだと思うし、バレンタインイベントにももはやリゼロッタさんの姿がない(ルシェンダ様も居ないので、もはや誰に入れていいのか分からなかった…)ところを見るとそんなに脚光を浴びることもなさそうだし、空き時間が来るたび、来るたび…ドラクエ本編もやらず、ケータイのメモを開いては、コツコツ…コツコツ…なんかこう…、二人が会える理由ないかな…なんかこう、どういう形でもいいんだけど、なんか…たとえばこういうのとか…って…。なんかもう夢とかでもいいから…。って…。
 わたし
わたし
あれからどれくらい月日が流れただろう。セレドの町に暮らす子供たちは、いつまでも子供の姿をしている。老いることのない死者たちはいつまでも元気に山道を走ることができた。もっとも、それは体力の話であって精神的には落ち着きが訪れ、必要な時に山道を走ることはしても、無邪気に野山を走り回る者はほとんど居なくなった。ダーマ神殿でのお祈りが長年続く日課になった者もいたが、祈る理由を失ってダーマへの石段をのぼろうとしなくなった者もあった。
あの頃と特段変わったのは、町の子供たちが自らの死を事実として受け入れたことだ。遺してきた家族と二つの世界を重ねた最初で最後の邂逅を遂げて以後、ほぼ全員が大人たちの居ない家に帰っていった。もちろん以前から自宅で過ごす時間はあったがそんなことは稀で、人恋しくなったり遊び疲れて帰るのが億劫になると誰からともなく「教会に泊まる」「帰らない」と言い出し、そうするとつられて全員がなんとなく帰宅を後回しにするのが常だった。ティールームの奥にはムッチーノが並べたベッドがあり、ほとんどいつでも満員だった。どうせ帰ったところで両親の温めてくれた部屋ではないのだ。だったら帰宅はただ面倒なものでしかなかった。
そんな堕落した暮らしが永久的に続くかと思われたが霊媒師サダクの企てとルコリアの機転によって不意に齎(もたら)された告別の時を経て、自らが置かれた状況を理解した子供たちはそれから暫くのうちに次々と、“その家に生まれた子供として”ではなく“家を治める主(あるじ)として”の帰宅を試み、遂には完了させたのだ。
高台の教会に寝泊まりすることも使い魔に頼ることも、豪勢なおやつを毎日食べることもなくなった。あれ以来、死してなお生きていくための覚悟のような灯(あかり)が、偽りのセレドの町を毎晩照らしている。ただ一人、高台の教会を離れなかったのはリゼロッタだった。正確に言えば、教会を離れなかったのではなく、家に帰れなかった。
もちろん他の子供たちと同様、実家に住まいを移そうと試みたことがリゼロッタにだって、ある。あの日は陽暮れを見計らって、ピンクと白のワンピースを包み隠すように暗色の外套を羽織ると、夕闇に溶けるようにして足早に路地を駆け抜けた。夜を待ったのも、外套を羽織ったのも、実家に向かった姿を誰にも見られたくなかったからだ。
予め、寂しさに負けて教会の自室へ帰る結末を実家に行くまでもなく知っていたリゼロッタは、孤独に敗北する姿を“国民”に見られるわけにはいかなかった。他の子供たちに遅れをとったのも、表向きは「悲劇の責任者として、全員が実家に落ち着くまで自分ばかり帰るわけにいかない」というものだったが、本音はただ、誰もいない家に帰る勇気が持てなかった。それでも一応「帰ってみよう」と思ったのは、新しい人生を始めなければならない運命への服従で、情けない女王の、せめてもの矜恃だった。
夜風がリゼロッタと外套の仲を割りながら通り過ぎていく。外套と言っても、以前ミザールと共にメルサンディ穀倉帯まで焼き菓子の材料を調達に行ったミラカが拾ってきた〈よるのとばり〉を首元で留めただけで、襟もなければ袖もないそれはとても見窄(みすぼ)らしいものだったが、リゼロッタは痛く気に入っていた。闇の中では黒く落ち着き、陽を浴びれば濃紺に透けるしっとりとした色味が、ルコリアのワンピースとよく似ている。
偽りの生家も、本物の生家も、玄関の前に石段があるのは同じだった。庭の片隅に積まれた薪も、干されたシーツまでも。
玄関のドアを開ける覚悟は大して要らない。生前、父の虫の居所の悪い日にこのドアを開ける時のほうがよほど緊張したからかもしれないし、自分の胸を掻き乱すドアがこのドアではないことが分かっていたからかもしれない。
中に入ると、よく知る間取りが広がっている。時おり応接にも使われる居間があって、奥には浴室。両親の部屋と姉妹の部屋に続く階段は玄関に入ってすぐ右手にある。ところが居間の暖炉は、薪こそ庭に積まれているものの、部屋を暖めた経験が無さそうに見えた。壁掛けの燭台も形ばかりそこにあるだけで、火が灯ったことはないのだろう。
暗い階段を上った短い廊下の奥に、こちらの世界のどこよりも気掛かりな部屋がある。
リゼロッタは重苦しい胸の奥を甘い思い出と痛切な後悔で満たしながら階段を上り、廊下を進んだ。俯いたまま、床の木目を虚ろな気持ちで見つめながら。
行くべき場所に辿り着いたリゼロッタがやっと視線を上げると、あまりにも地味だった。そのドアには本当なら“二人の色”を表した飾り布があるはずなのに、ただの木戸が突っ立っているだけなのが不服だった。こちらの世界はリゼロッタの孤独に対して素っ気ない。退屈な木のドアを思い切って開けると、やはり誰も居ない。知っていた。ルコリアは居ない、いや、“私がもう居ない”のだ。そこには確かに見覚えのあるような、しかし絶対に訪れたことのない、懐かしい部屋が広がっている。
リゼロッタは不思議だった。懐かしいし、何もかも知っているのに、「自分は絶対ここに来たことがない」と解る。
ルコリアと過ごした“ほんとうの部屋”には、二人の気に入りの色で作られた飾り布が天井から壁に張り巡らされ、揃いの家具にもそれぞれの色に染め上げた布がかけられていた。2台並んだベッド。2台並んだ鏡台。2台並んだ本棚。2台並んだタンス。唯一1つしかないのはいつも二人で囲んでいたテーブルだったが、対になった2脚の椅子が団結したみたいに、“ほんとうの世界”ではあのテーブルを挟んで並んでいた。
きっとルコリアは寂しさを紛らわせるために、私が遺してきた大きな縫い包みを私の椅子に座らせていることだろう、と、リゼロッタは思った。
ルコリアのワンピースと同じ色をしたカーテンは、夜になれば闇を遮り、朝が来れば光を取り込んだ。ルコリアの色のカーテンを束ねるタッセルは、リゼロッタの色で作られていた。姉妹の部屋にあるいずれの家具も、二人の在り方を象徴している。象徴していたはずだ。それなのに、偽りの二人の部屋は、あまりにもリゼロッタたちの在り方を偽っている。
偽りの自室を慎重に見回してみると、まず辛うじて室内には再現された飾り布だが、色がおかしい。廊下のドアに何も飾られていなかったことを思えば布があるだけで上出来だが、布の全てがルコリアのワンピースのような濃紺で、リゼロッタが好んで身にまとうピンクの生地が見当たらない。まるで自分が妹から引き剥がされたような仕上がりなのだ。
テーブルだけは数を変えずに1台あったが、傍にあった椅子が1脚どこかに消えて、1脚だけが残されている。色を見る限り残った椅子がルコリアの椅子で、消え去った椅子がリゼロッタの椅子のようだった。ベッド、本棚、鏡台、タンスはすべてリゼロッタのものがなくなっているが、これは偽りのセレドができた時、すでにこうなっていたのだろうか。
或いは…。
思い出されるのは“大人たちが消えた日”の翌朝のことだ。前日に魔人召喚に失敗した子供たちの前に現れたのは羊の体に小太り男の上半身をつけたヘンテコな使い魔で、名をムッチーノといった。
「女王様の御心は、ワタクシめの心。」
現れるなり宣(のたま)った彼の言葉と傅(かしず)く姿を真似て、町の子供たちはリゼロッタを「女王様」と呼び、従うようになっていく。最初はきっと、この格式張った姿勢と言葉が「お城みたい!」に、「グランゼドーラの王国みたい!」に思えて、山間(やまあい)の小さな町で育った子供たちはワクワクしたのだろう。リゼロッタはこの不可解な外見の魔物の言葉に、盗み見たルコリアの日記に時々綴られる「姉さんの望みは私の望み」という言葉を重ねて、早くも気を許していた。
事故の当日はムッチーノを含め、全員が高台の教会で夜を明かした。フィーロは終始沈んだ様子を見せていたがそれは今後への憂慮と言うより目の前の光景への困惑であって、あの段階ではまだ「大人が一時的に消えた」と認識している子供たちの中に「自分たちが今後どうなるか」の想像に取り組む者は見当たらなかった。
子供だけで迎える初めての夜は、夢の王国としか言いようがない。早くベッドに入るよう促されることもなく、全ての我侭に対し首を縦に振る従順な家来まで現れた。ムッチーノの出した豪勢なお菓子に囲まれて、好きなだけ夜更かしをする。興奮で満たされた一夜だった。子供だけで街に繰り出し、星を見上げて歩く。大声で歌を歌っても叱られないなんて、どんな夢だろう。そう、これはもしかしたら魔人の奇跡が私たちに見せている甘い夢なのかも知れない。明日の朝起きたら、どうせいつもみたいに父さんに寝坊を叱られて。でも、夢でもいいからルコリアにもこの解放感を味わわせてあげたい!何気なく、しかしリゼロッタは本気で願った。人生はもしかすると自由を手にすれば楽しいのかもしれない!と、いとも気軽に、しかし心から思えた。
その、人生というのが、ついさっき終わったとも知らずに。
おやつも食べ飽きて、遊び疲れた子供たちが駄々をこね始めたのとちょうど同じ頃、真実の世界ではセレドの大人たちが夜を徹して瓦礫(がれき)の中から我が子を探し終えたところだった。
生きている筈、気を失っているだけだ、と、すがるような祈りを胸に大人たちは我が子の名前を叫び続けたが、返事はない。瓦礫を掘り続けた手は男も女も関係なく血だらけで、最も大きな石壁を大人たちがやっと退けると、一人目の背中が見えた。無言よりも遥かに静かな沈黙が小さな背中にこびりついている。次々と施療院に運び込まれる子供たちが助かることを誰もが祈りはしたが、信じることは難しかった。一方ルコリアは、松明の火に照らされて暗闇からひとり、またひとりと運び出される友達を一瞥ずつ目で追いながら、すぐに瓦礫の山に視線を戻し、ひたすら姉の生還を待ち続けた。自分も瓦礫を掘ろうと何度も駆け出したが、その都度大人に引き戻される。他の子供達が、つまり友人達が次々と無言で現れることに絶望するものの、それは平坦な絶望で、心はわざわざ動かなかった。ただ一人、姉の、リゼロッタの姿を見つけた瞬間、動くためだけに、ルコリアの心は静かに押し黙ってその時を待っているようだった。
「あとは、町長さんちのリゼロッタお嬢さんだけか…。」
そう呟いたのはドラウという見た目は荒くれ者だが人一倍面倒見のいい大男で、自分に子供が居るわけでもないのに、痣や切り傷を作りながら懸命に瓦礫を掘っている。
このまま見つからなければいっそ「姉さんは魔人とどこかに出掛けただけ」と信じられるのに、と考えた瞬間、ルコリアの目に飛び込んできたのは、ぼろぼろに煤けて破れた薄いピンクの布地だった。
下がっていないはずの熱も、ずっと出ていたはずの咳も、脈打つように痛かった頭も、駆け出した足が縺(もつ)れて石畳に激しく転んだたった今の出来事も何もかも忘れるほど無我夢中で抱きついた姉の体は、ルコリアの抱擁を拒むようにミシミシと硬くなっていたが、当のリゼロッタはそんなことを知る由もなく、偽りのセレドで睡魔と闘いながら、他の子供たちと呑気に寝床の心配をしている。すっかり空が白んできた、事故の翌朝のことだ。
リゼロッタが出来心で半人半羊の使い魔に寝床の支度を命じると、ムッチーノと名乗るヘンテコな使い魔はどこからともなくベッドを見繕い、高台の教会の広間に設置した。
「女王様の御心は、ワタクシめの心。」
後にティールームとなるこの部屋が子供たちの溜まり場になったのは、思えば最初にベッドが来たからかも知れない。
これがリゼロッタからムッチーノへの、初めての命令だった。リゼロッタはこの便利でおかしな使い魔を一刻も早くルコリアに見せて、いつものように「さすが姉さん!」と言われることを眠い頭で妄想している。どうせ夢なら、ルコリアも早く夢の世界に来てくれればいいのに。
年下の子供たちはベッドが来るなり皆すぐに寝ついてしまい、やや年長の子供たちも幼児たちの隙間をぬって次々と眠りに落ちた。悪夢から醒めるよう神に祈りを捧げたフィーロも「眠れば大人達が戻ってくるからリズも祈るべきだ」と、譫言(うわごと)を繰り返しながらいつの間にか寝つき、最後まで起きていたのはリゼロッタだった。ルコリアが気がかりという精神的な問題もあったが、そもそもベッドに空きがないという物理的な問題もあって横になることすらできなかった。
 GameBlog|プレイスキル0
GameBlog|プレイスキル0