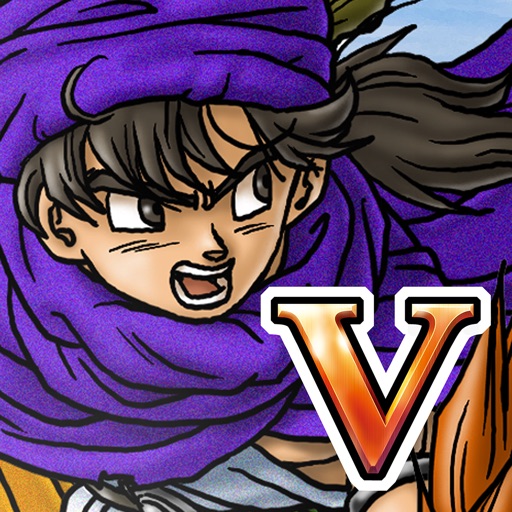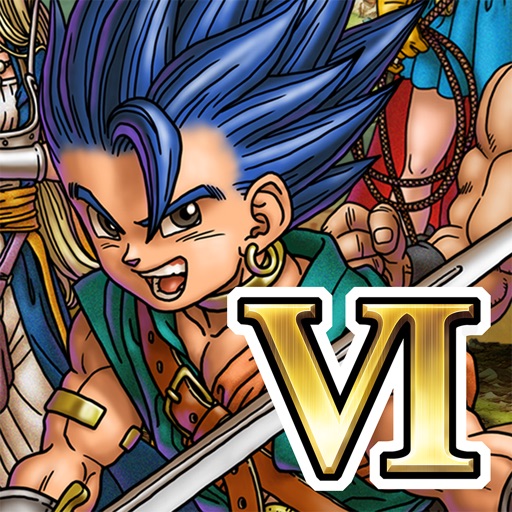床には寝たくない。だからといって、こんな時間に帰宅できるだろうか。ただの夢ならばいいけれど、もしもこれが魔人の見せている幻や魔術の効果だとしたら。大人たちが消えたのは見せ掛けで、もしかすれば今頃は家族が全員自宅に戻っている可能性もあると思うと、父親からどれほど厳しい叱責を受けるだろう。恐ろしくて戻れない。いずれは帰らなければならないが、今は眠気で手頃な言い訳も思いつかない。悩んだリゼロッタは再びムッチーノを呼び出すと、家具を教会の空き部屋に持ってくるよう命じた。
「女王様の御心は、ワタクシめの心。」
ムッチーノは教会から離れることなく、魔術でリゼロッタのための家具を揃えた。この時の成り行きで、二階の部屋は女王の居室となる。
リゼロッタが高台の教会でベッドに入った頃、ちょうど真のセレドの町でも永遠の眠りについたリゼロッタが眠り慣れたベッドに乗せられたところだった。両親と共にリゼロッタを連れ帰ったルコリアは、煤けた姉の顔を湯を含ませた布で丁寧に拭いてやりながら、幾度も「姉さん」「姉さん」と呼び掛けてみる。返事はない。両親はリゼロッタの父母である前に“町長夫妻”として犠牲になったすべての子供の家を周ることを選び、ルコリアに留守を、ひいてはリゼロッタの身の回りの世話のすべてを託し、血も涙も拭くことをしないまま足早に出て行った。無理もない。「町長の娘と遊んでいたら全員が亡くなった」なんて、父の性格を思えば我が子を失おうとも悲しんでいる場合ではないとルコリアは嫌というほど知っていた。
リゼロッタの体は冷たく硬く、両手は咄嗟に頭を庇うような仕草をしたまま顔の両脇で固まっていた。ルコリアは、最期にこんな姿勢をとって瓦礫の中に居た姉の心細さを思うと、ただただ自分が代わってやりたかった、せめて傍に居て一緒に逝ってやれたらよかったのにと自分の運の無さを呪った。
「姉さん…、怖かったわね…。」
顔を拭き終えたルコリアは硬くなった姉の手と優しく握手するように、今度は指の一本一本を付け根まで拭き、爪と指の間に挟まった砂を取りながら時折リゼロッタの顔を覗き込む。桜色をしていたはずの唇はすっかり色を失っている。ふと気づき、ルコリアはリゼロッタの首元に片手をやると器用に留め具を外し、破れてしまったピンクのマントを外した。お揃いの服を着続けた姉妹だからこそ出来る慣れた手つきだった。
「こんな出来事の名残を、いつまでも身につけている必要はないわ…。姉さんが最後に味わった恐怖ごと私が持っててあげるから貸して…。」
ぼろぼろと涙を零したままルコリアが優しく微笑むと、リゼロッタのほとんど閉じた瞼の隙間からほんの少しだけ見える綺麗な水色の眼と目が合った。ルコリアはリゼロッタの冷たい顔を包むように撫でながら、乱れた髪を整えた。
「姉さん。」
前髪の上で結ばれたピンクのリボンを優しく解くと、髪がこごってしまわないように注意深く頭の下から抜いた。時おり頼まれてリボンを結んだり解いたりする時は体温を感じるのに、今日はリボンも髪もひんやりとしている。
「これも少し苦しいかしら。…どう?」
腰を締めているリボンに指を掛けながら尋ねてみる。
「でも姉さんは昨日の朝から何も食べていないから、大して苦しくないかしら。姉さん、どう思う?それよりお腹が空いた?」
返事はなかったがルコリアは気にせずリボンを解いた。気にしたらまるで、姉が亡くなったことを、本当に返事がないことを、認める羽目になってしまう気がして。だから、姉の意思を無視するつもりで無言など意に介さず、ルコリアはリゼロッタの体を締めているすべてのものを外した。靴を脱がせ、破れたタイツを両足から取り払い、解けたリボンを腰の下から抜き取ると、すっかり白いワンピースだけに身を包まれた姉が横たわっていて、まるで元より死装束を着せられているように見える。徐(おもむろ)に自らのリボンとマントを解いたルコリアは、
「私、喪服みたいね。出来過ぎだわ。」
そう言って二人分の鮮やかな衣類を畳み、自分のベッドに乗せた。ルコリアの目の前で自身が亡くなっていることなど知らないリゼロッタは、偽りの世界で祭壇に腰掛けて足を組み、ムッチーノをこき使っている。
(ルコリアに会いたいわ。一人で眠ったことなんてないのに…。)
ムッチーノが教会に持ってきたベッドと鏡台は自分の部屋にあったままの姿形をしており、一方、本棚とタンスはピンクの掛け布がなくなっていた。テーブルは形こそ同じだったがクロスの色は濃紺からピンクに変わっていた。紺色と紅色が1脚ずつしかなかったはずの椅子はどういうわけか紅色のものが3脚になって届いている。
この町に来た当時のリゼロッタは「ムッチーノが我が家にあるものを魔術で増やした」くらいに思っていたから大して気にしていなかったが、月日が流れて、このセレドがどういう町なのか自身の身に何が起きたのかを正確に理解してから偽りの自室を見回すと気になることだらけだ。
もしかしたらムッチーノはここから家具を移動させたのかも知れない。仕組みはよく分からないが、魔法が掛かる途中で家具が数や姿を変えたり、掛け布が失われたりすることもあるのだろうか。いやしかし部屋に張り巡らされた色のおかしな飾り布を見ると、そもそもこの街自体が質の悪い複製のようにも思えてくる。壊れた教会だって場所が違う。本来遊び場になっていたのは古い教会で、“原因不明のガケ崩れ”が起きたとすれば壊れているのは高台に建つ古い教会のはず。であるにもかかわらず、こちらのセレドの町では町の中にある教会が崩れている。あそこは姉妹の父である町長のブラトと、フィーロの父であるフィブラ神父が中心となって新しく建てた教会で、魔人召喚の儀式を行った場所ではない。光の河も消えてしまった。この町は、ところどころ、何かがズレているのだ。
自室のドアを開けた時に感じた間違いなく見覚えのある懐かしさと、しかし何もかも知っているのに自分は絶対ここに来たことがないという確信の理由は、これらの違和感から来ていた。
窓にかかったカーテンだけは真実の世界でも偽りの世界でも同じ仕上がりで、ルコリアのワンピースと同じ色をした生地を、リゼロッタの色で作られたタッセルが束ねている。まるで自分がルコリアを縛り付けているようにカーテンは束ねられたまま、夜だというのに闇を遮ることなく、真っ暗な窓の外をリゼロッタに見せつけた。暗闇を遮り、光を取り込んでくれたのはいつだってルコリアだったのに。天井の飾り布は押し黙って垂れて、懐かしさと虚しさが重たい空気にべっとりと重なっている。
夕暮れになるとカーテンを閉めるよう催促するのはリゼロッタの日課だった。
「ルコリア、あなたいつまで外を見ているつもり?早く寝て明日の支度をしないといけないのに。」
嫌味を言って、本当は窓から見える夜の闇が苦手だっただけだ。朝になると、
「ルコリア、このまま夜まで寝続けるつもり?」
なんて催促をして、朝の光で部屋を満たしてもらった。本当はベッドにもぐったまま、朝陽の中で気持ち良く微睡(まどろ)んでいたいだけだった。ルコリアは物静かなだけで、本当は人が思うよりしっかりしている。朝起きるのが苦手な私よりテキパキと動いていたし、カーテンを閉めないこと自体は少しずぼらな気がするけれど、私のように「闇夜を恐れて」という理由を持つことなど一度もなかった。夜は暗くて怖くないか聞いてみても「どうして?」の一言で片付けられてしまう。リゼロッタがルコリアより優れていると自負できるのは、強気な態度と字の美しさだけだった。それでも、ルコリアのほうが慎ましくて人に好かれたと思うし、字だってルコリアの書く文字には愛嬌があって、本当は自分の字よりも好きだった。
偽りのものと知りながらルコリアのベッドに寝転んでみると、どこから来たか分からない埃が舞い上がる。リゼロッタはケホケホと噎(む)せた。死後の世界で部屋が汚れるなんて考えてみたこともなかったのに。
 GameBlog|プレイスキル0
GameBlog|プレイスキル0