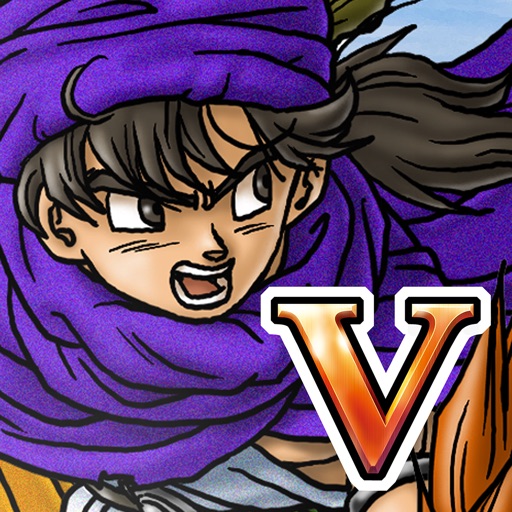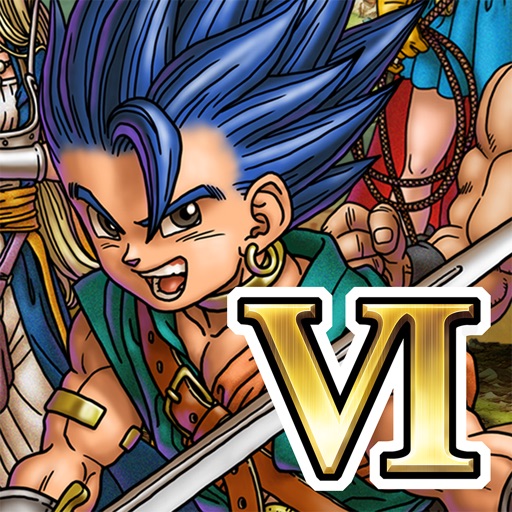あの日、魔人召喚の儀式に参加しようと起き上がったルコリアを制止したこのベッドは、“このベッド”ではない。ここはどこなのだろう。死後のセレドだけれど、それはつまり、空の上なのか、地上の下なのか、遠い星なのか、同じ場所で並行しているのか、距離にしたらルコリアからどれくらい離れた場所なのか、リゼロッタにはよく分からなかった。もしかしてお互いに姿が見えないだけで、ルコリアはこの街にいるのだろうか。でも、だったらベッドから舞い上がった埃の説明がつかない。居るならきっと、綺麗なベッドが保たれているはずだ。もっとも、あれからだいぶ年月が流れているからルコリアはとっくにどこかの良家に嫁いだかも知れないけれど。
儀式の前日に発熱し咳き込んでいたルコリアを、自分の咳の音で思い出す。あの後すぐ、風邪はよくなっただろうか。熱は下がっただろうか。
成功したら、ルコリアから「さすが私の姉さん!」と一日中賞賛を浴びる予定だった。自尊心を満たしたいわけでも、妹の上に立ちたいわけでもない。ただ、ルコリアからの無垢な賞賛は、甘えるのが上手くないリゼロッタにとって人の温かさに包まれるような瞬間だったし、「仕方ないからあなたにも見せてあげるわ」というのは、本音では一人で何かをするなんて心細くて気が進まないリゼロッタにとって、ルコリアの傍に居るための丁度いい言い訳だった。
内心、ルコリアが同席しないのなら儀式なんてやめてしまいたかったが、周りの子供たちは魔人の召喚を楽しみにしている。「成し遂げなければ」という責任感と、「成し遂げてみせる」という意地で中止を言い出せなかったリゼロッタは、熱で火照ったルコリアの額に手を当て、わざと嫌な顔をしてみせた。
「こんなに熱があるあなたを連れ出したら、私はどれほど叱られるかしら。」
ルコリアは少し黙って考えてから、
「そうね。」
と残念そうに微笑み、ベッドに体を横たえた。
「姉さん、戻ったらどんなだったか教えてね。」
「……………ねえルコリア、うまくいくかしら…?」
リゼロッタは胸の奥底で疼(うず)く不安に蓋をするように尋ねる。生まれてこのかた、食事を摂りに階段を降りるときだってわざわざお互いを待って一緒に生きてきたのに、こんな大事な時に限って傍に居られないなんて。
リゼロッタの不安を打ち消すようにルコリアは、
「姉さんらしくない。もちろんよ、姉さんはなんだってできるんだから!」
と、大きく微笑み直した。
認め、常に信じてくれるのも、何をしても叱らないでいてくれるのも、ルコリアだけだ。リゼロッタはこの時もルコリアに抱きつきたい思いでいっぱいになったが、隣の部屋で父の気配がしたので、素っ気ない態度を貫いた。自分が誰かに甘えた気配すら、どこにも残したくはなかった。「しっかりすること」は、誰にも頼らないことだと思っていたし、父が求めるような「立派な人間」として一人前に認められるためには、妹の温もりに一喜一憂などしていられない。
(願いを叶えてくれる魔人と会えたら、何を頼もうかしら。皆は「お菓子がたくさんの子供の王国を作る」なんてつまらないことを言っていたけれど、まずはルコリアの熱をすぐに下げてもらえないかしら。)
そんなことを思いながら階段を降りたことを憶えている。あの階段も、今、こちらのセレドで自分が上ってきた階段とはきっと違うものなのだ。自分の家なのに。ここはセレドなのに。
ルコリアのベッドに敷かれた偽りのシーツは、「どこかにルコリアが居ないだろうか」と願う淡い期待を予め裏切るほど、ピンと張って冷たかった。
リゼロッタはドアをそっと、しかしかたく閉ざして、高台の教会への道を戻った。石段を降りた曲がり角にある井戸の蓋が閉まっているのは、生前のセレドも死後のセレドも同じだ。町長である父が「子供が落ちないように」と持ち主を説得して閉める習慣をつけさせた。
角を曲がると橋の向こうの高台に教会が見える。結局あそこに帰ることになるのだ。もとよりそうなるだろうと想像はしていたけれど、改めてそう認識すると覚悟の甘い自分を腑甲斐なく思う。
町の子供たちについて、“親と離れ離れになる寂しさ”は全員に完璧に等しかった。それでいて、兄弟姉妹を持つ者は一人を除いて漏れなく“兄弟姉妹揃って命を落とした”ため、死後のセレドにおいて天涯孤独になることはない。また、もともと一人っ子として育った子供は、家族と離れる寂しさこそあるものの、“自室に自分しか居ないこと”に対してだけは疑問も違和感も湧いていないようだった。あらゆる家具が2台仲良く並ぶ子供部屋を失う試練に見舞われたのは、唯一リゼロッタだけで、最も親しい同世代の家族を失ったのも、唯一リゼロッタだけ。この繊細な差分に気づきリゼロッタの心を支える子供は、誰一人としてこちらのセレドには居ない。もちろんリゼロッタも自分が誰より辛いなんてことは思っていなかったし特段に気遣って欲しいなどとは露ほども思わなかったが、自分の気持ちを正確に分かってくれる人間はもうこの世界に居ないのだという事実に、言いようのない行き詰まりを感じていた。
ルコリアさえいてくれれば。
取り返しのつかないことをした恨み辛みが己に襲いかかってくる。なぜあのとき引き返さなかったのだろうと百万回思っても、たった一度の実行を後から塗り替える術は無い。せめて自分が命を落としたことが救いで、安いけれど、最善の贖罪だったのかもしれない。他の子供が亡くなった中で自分ばかり生き残ってしまっていたら、街の誰にも顔向けができなかっただろう。きっとそれだけでは済まない。厳格な父などは責任を感じて自ら命を絶ったかもしれないし、もしかしたら、一家全員で…。そう思えばこれは、不幸中の幸いだったのだ。言い聞かせるように小刻みに頷きながら、リゼロッタは偽りの崩れた教会跡地に差し掛かる。
瓦礫の山と割れガラスの海を子供の腕力と注意力だけで安全に片付けることは難しく、女王からも親衛隊からも「崩れたら危ないから近付かないように」「手を切るといけないから近付かないように」と再三お達しを出していたため、ここは依然としてステンドグラスが散らばったままだ。それを覆い隠すように草花が萌えているのは、騙し騙し日々に安寧を見出している自分とよく似ている。そう思いながらリゼロッタは、崩れた教会の前を足早に通り過ぎた。
もともとこの教会跡地でシスターとして神に仕えてきたラーニに加え、今ではフィーロも神父を務めるようになった。高台の教会を使わずに野ざらしの教会を続ける理由をシスター・ラーニもフィーロ神父も明言しないが、恐らく、高台の教会で暮らし続けるリゼロッタへの遠慮だろう。
自分さえ出て行けばラーニもフィーロも屋外に勤めなくて済むのに。気掛かりに思いながらもリゼロッタは、高台の教会に続く“帰り道”を歩き続けた。橋からは各々の家の主となった子供たちの灯す明かりが見え、渡り切ると料理屋から夕食を愉しむ子供たちの大きな笑い声が聞こえたが、リゼロッタの心は重く暗く静まり返っている。
高台の麓まできて、来た道を振り返る。ポツンと自分だけが立っている道に風が吹いた。空を見つめても、町を見つめても、感傷に浸っても、過去を悔やんでも、望むものは何も変わりはしないのだ。歳をとることもなく、老いることもなく、この世界で、ずっと。自分も変われないし、世界はきっと、もっと変わらない。世界を徹底的に滅ぼしてくれる者でも現れない限り変わりはしないし、仮にこの世界が滅ぼされるなら、それはそれで相応の恐怖から逃れられないだろう。何がどう転ぼうと報われる道は無さそうだ。
教会までの石段を一段一段上る足取りは重く途中で諦めそうになったが、駄々をこねたところで孤独なのだと思うと諦める気力さえ湧かなかった。ただそういう機構のように、心無く高台への階段を上りきる。
振り返ると石垣の向こうに偽りの我が家が見えた。灯りのない家の赤い屋根は闇に紛れて、幸せの気配も、不幸の気配すらも無く、ただ、淡々と聳(そび)えていた。
かつてボッシュが槍を構えて守っていた教会の扉に今は人影も無く、扉は自分で開けるしかなかった。リゼロッタは無言のまま凸凹した鼠色の大扉に両の掌をあて、一瞬強く体重をかけた。少し腰を入れないと子供の体では開けにくい扉が、ギイと音を立てる。むかし、年老いた町民が体の不自由を嘆いていたのを聞いたことがあったが、年老いることがないのも不自由なのだとリゼロッタは知った。“大人になる予定”というのは子供特有の不自由を黙認して過ごすために必要な希望の火だったのだと予定を失った今は思う。
入るなり緑の毛氈(もうせん)に崩れたリゼロッタは床にぺたんと座り込んだまま暫し、ぼんやりと小さな礼拝堂を見つめていた。何を見ていたわけでもないけれど、目に入った景色を拒むことなく、ただぼんやりと住み慣れた教会の景色を目に入れて途方に暮れた。自分はなぜこんなところに居るのか、疑問の答えは知っていたが、問い掛けが消えることはない。毛氈の先には祭壇があって、その奥には色鮮やかなステンドグラスがあるはずだが、夜になると闇に色がベタッと乗っただけの厚い硝子でしかなかった。ステンドグラスの両脇に立つ燭台の蝋燭は、留守の間に蝋が溶け切って火が消えていた。石畳の床は毛氈を敷いたところで、どのみち硬かった。
 GameBlog|プレイスキル0
GameBlog|プレイスキル0